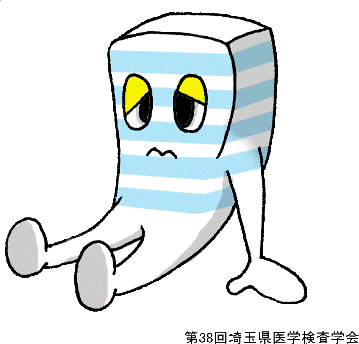
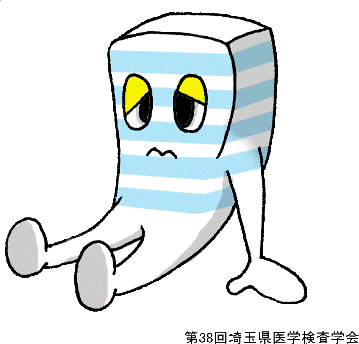
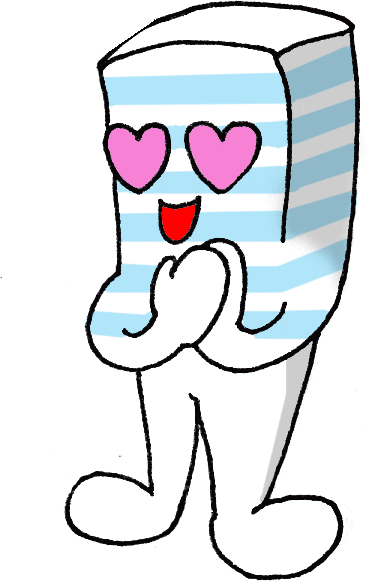
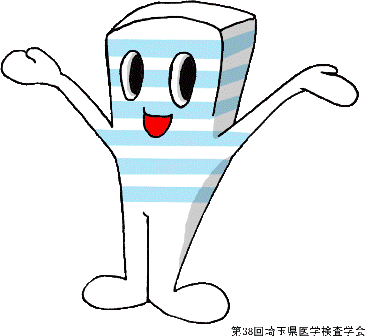
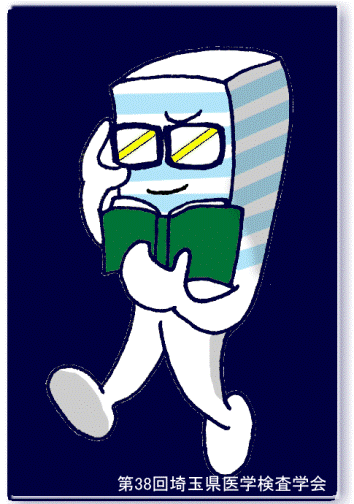

「今日から役立つ臨床検査 ~来て、見て、聞いて、不安をなくそう~」をテーマに、身近な問題を取り上げ、より多くの会員に参加してもらえる学会を目指し、身近で日常業務に役立つ実践的な学会企画として、
「採血業務について」
「検査室運営について」
「日当直検査業務について」
の3つのテーマでセミナーを開催いたします。昼のランチョンセミナーと午後の実践セミナーを連携させ充実した内容となるよう企画しています。
![]()
STEP UP! 検査技師のあり方
激動する医療改革の中,「これからの検査室運営は?我々が行うべき検査室改革と生き残りへの道は?臨床検査技師は病院の中でどのような役割を担うことが可能なのか?」など,検査室の管理と運営がテーマとなるセミナーを開催いたします.
この企画の根幹となる現状の検査室について杉山先生にわかりやすく分析解説いただき,今後の検査室と検査技師の方向性を「処方箋」としてご教示願います.引き続き学術セミナーで,感染症対策と院内委員会活動における臨床検査技師の役割と何ができるのか実践例を連携させ,「今日から役立てられる実践的セミナー」となるよう企画しました.
講師:杉山 誠 先生(臨床検査メリトクラシー研究会顧問,湯河原胃腸病院 事務長)
司会:五内川 里子((社)埼玉県臨床検査技師会会長,埼玉社会保険病院)
協賛:(株)シスメックス,(株)ロッシュ・ダイアグノスティックス,(株)シーメンスメディカルソリューションズ・ダイアグノスティックス
![]()
講師:霧島 正浩((株)ビー・エム・エル)
講師:柴崎 光衛(獨協医科大学越谷病院)
司会:西田 俊朗(埼玉県立小児医療センター)
![]()
SKILL UP! 採血業務
採血業務は,患者との接遇や採血事故など多くの問題要因と背中合わせで日常業務として実施されています.担当者はいつも不安とプレッシャーの中,業務を行っているのが現状です.採血業務の手技や注意点を再確認し,インシデント・アクシデント情報等を共有しながら業務改善とトラブル防止に役立てていくことが必要です.「採血業務の注意事項」として,藤田先生に医療行為として採血業務をとらえ,採血方法,採血部位の注意点,VVRの早期発見ポイントなど,この企画の根幹となる部分をご教示いただきます.学術実践セミナーでは,採血業務を実施している代表施設より採血業務の実際とインシデントの状況を,生情報として報告していただきます.さらに採血に伴う医療訴訟の現状を知り,傷害保険の重要性の考えていく機会を提供いたします.フロアーからのディスカッションも加え,充実した内容のセミナーを目指します.日常業務として採血を行っている方は必見のセミナーです.
講師:藤田 浩 先生(東京都立墨東病院 輸血科 医長)
司会:津田 聡一郎((社)埼玉県臨床検査技師会 副会長,(株)ビー・エム・エル)
協賛:(株)テルモ,(株)積水メディカル
![]()
講師:大野 優子(埼玉医科大学総合医療センター)
講師:浅田 牧子(上尾中央総合病院)
講師:岩本 英久 先生(東京海上日動火災保険株式会社)
司会:袴田 博文(上尾中央医科グループ協議会)
![]()
BRUSH UP! 日当直業務
学会実行委員会より会員各施設にご協力をいただいた,「日当直業務に関するアンケート調査」の集計結果を報告いたします.「学術企画」として日当直検査のアンケート調査解析とアンケートから見えてくるこれからの日当直業務について解析報告を行います.アンケート調査解析は時間外検査の現状を把握し検査項目を見直すことにより,日当直時でも充実した検査体制確立すること,また日当直における多くの問題点を共有し改善を進めて行ける機会となるはずです.当日アンケート集計資料を配布します.続く「学術実践セミナー」では時間外血液型検査,クロスマッチ検査,危険な心電図波形とその対応,形態学としての髄液検査の実施と分類法の確認についてなど,時間外ではどのように実施し対応するべきか基礎的内容から時間外マニュアルとなりうる拠り所となる講演を行います.日当直実施者は必見のセミナーです.
講師:小峰 雅子(東松山市立市民病院)
講師:武関 雄二(自治医科大学附属さいたま医療センター)
司会:砂川 進((社)埼玉県臨床検査技師会 副会長,越谷市立病院)
![]()
講師:山田 攻(埼玉医科大学病院)
講師:柏原 敦(三郷中央総合病院)
講師:奈良 豊(埼玉医科大学総合医療センター)
司会:横川 昭(川口工業総合病院)
![]()
STAGE UP! 糖尿病療養指導士とは
糖尿病の患者数は全国820万人,予備軍を含めると1870万人と言われる国民病である.すでにご承知のとおり糖尿病には1型と2型がある.糖尿病の大部分を占める2型では,遺伝的要因に加え,運動不足や栄養の過剰摂取,肥満,喫煙などが要因として挙げられる.治療には生活習慣を改め,糖尿病の疾患と合併症,カロリー計算などについて患者自身が十分な理解を持つことが必要であり,臨床の現場では糖尿病療養指導士が大きな役割りを担っている.失明の原因となる網膜出血,増え続けている人工透析に至る腎不全,神経障害に伴う神経麻痺や下肢の感染と重症例における切断など,糖尿病に伴う極めて重大な合併症を予防する役割りを担っている糖尿病療養指導士.日本糖尿病学会等による研修と認定を受けた糖尿病療養指導士は,看護師,管理栄養士,薬剤師についで臨床検査技師が多い.認定教育施設の糖尿病療養指導士は,1施設あたり平均9.8人,糖尿病療養指導士1人あたりの患者数は110人と報告されている.本年度よりフットケアに対し一部保険が適応になるなど,社会的にもその役割りが認められている.糖尿病療養指導士とは,どんな資格か?取得するにはどうしたらいいか?どのような活動を行っているのか?患者のために我々は何ができるのか?など今後の臨床検査技師のSTAGE UPとしての糖尿病療養指導士セミナーを企画いたしました.すでに糖尿病療養指導士として活動している方,これから取得を目指そうとする方にも役立つ内容となっています.
講師:小関 紀之(獨協医科大学越谷病院)
司会:橋爪 英文(さいたま赤十字病院)